裏千家 四ヶ伝【風炉・唐物】点前
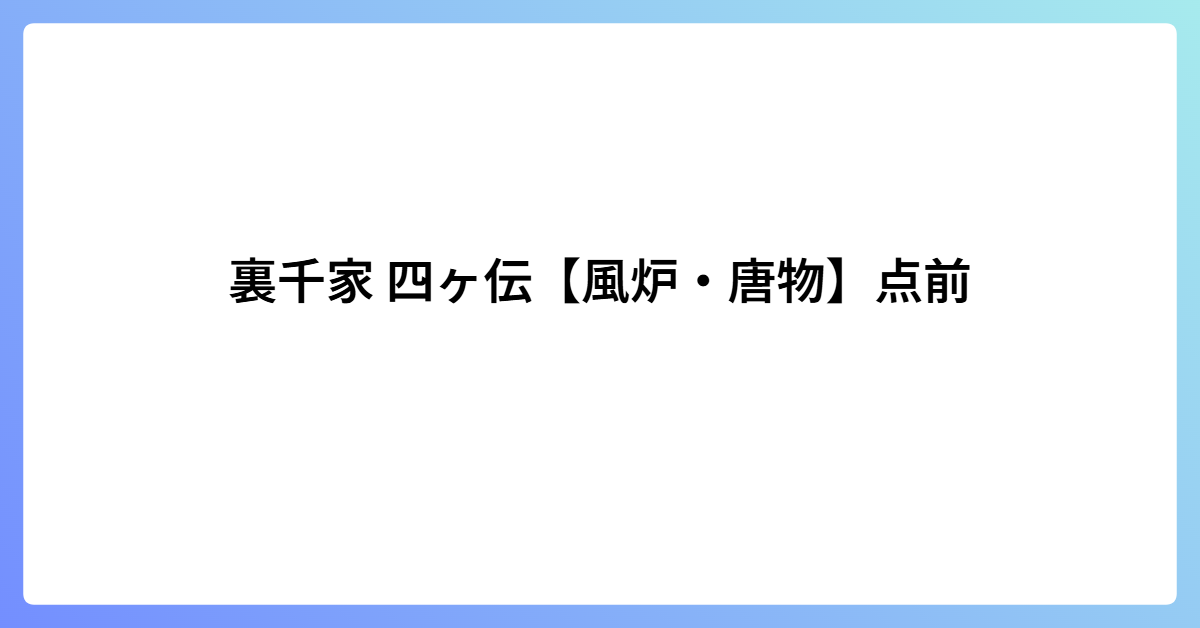
まいど、きょんたです!
この記事では、唐物のお点前の流れを整理し、間違えやすいポイントを分かりやすくまとめてみたで。
四ヶ伝の学びを深めたい人にとって、実際の稽古や復習の参考になる内容になったら、うれしいで。
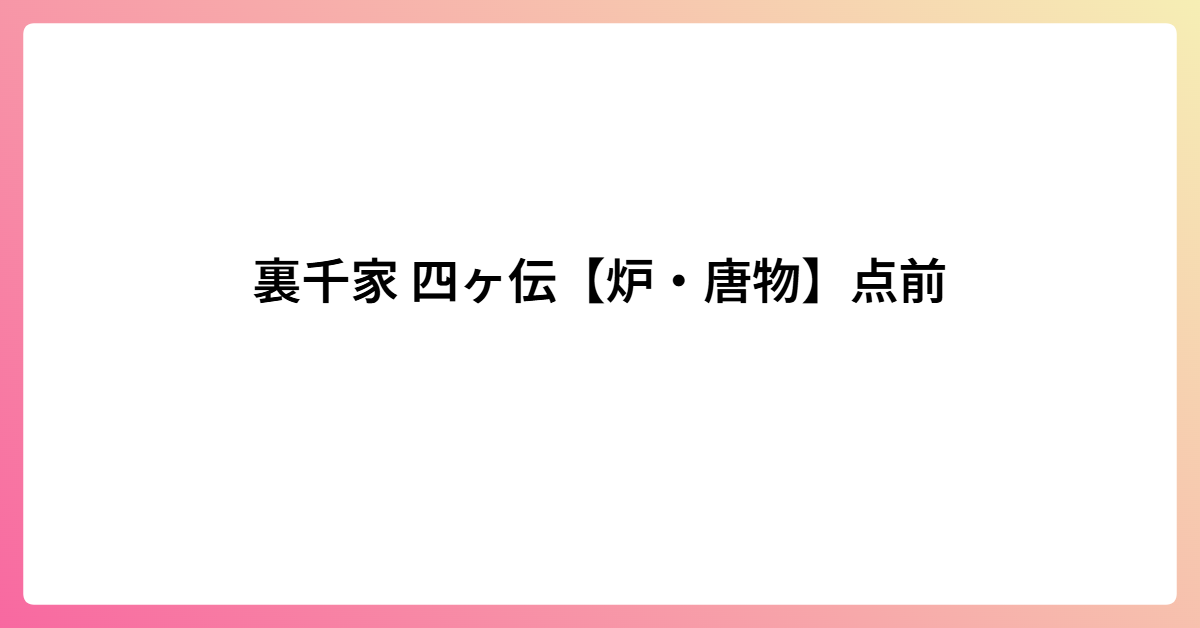
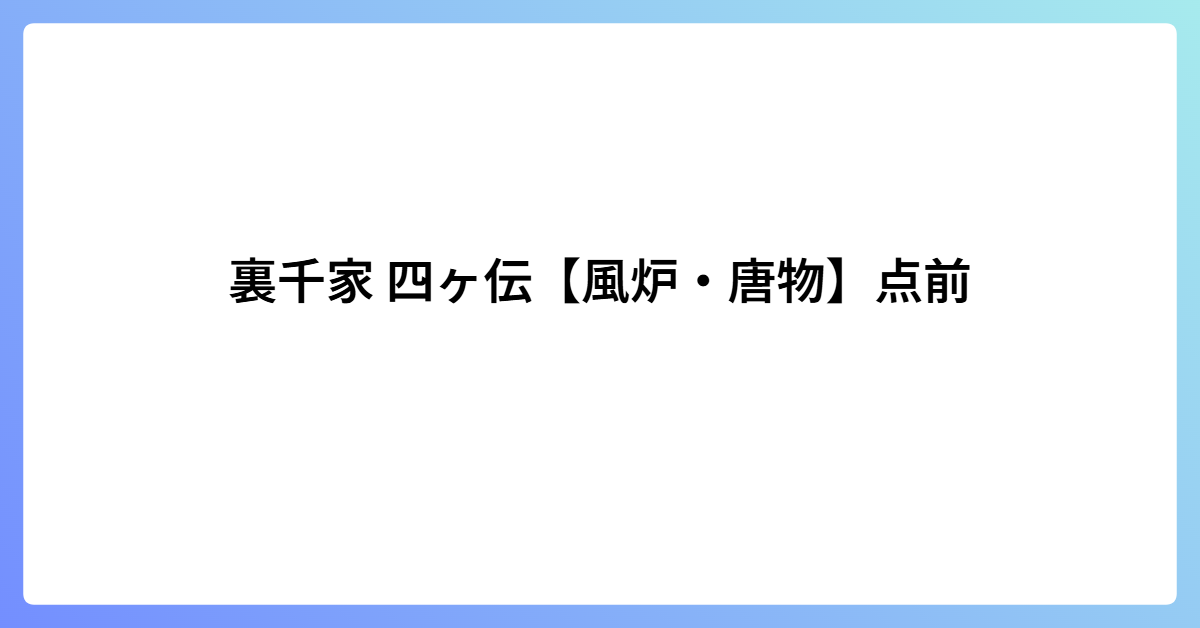
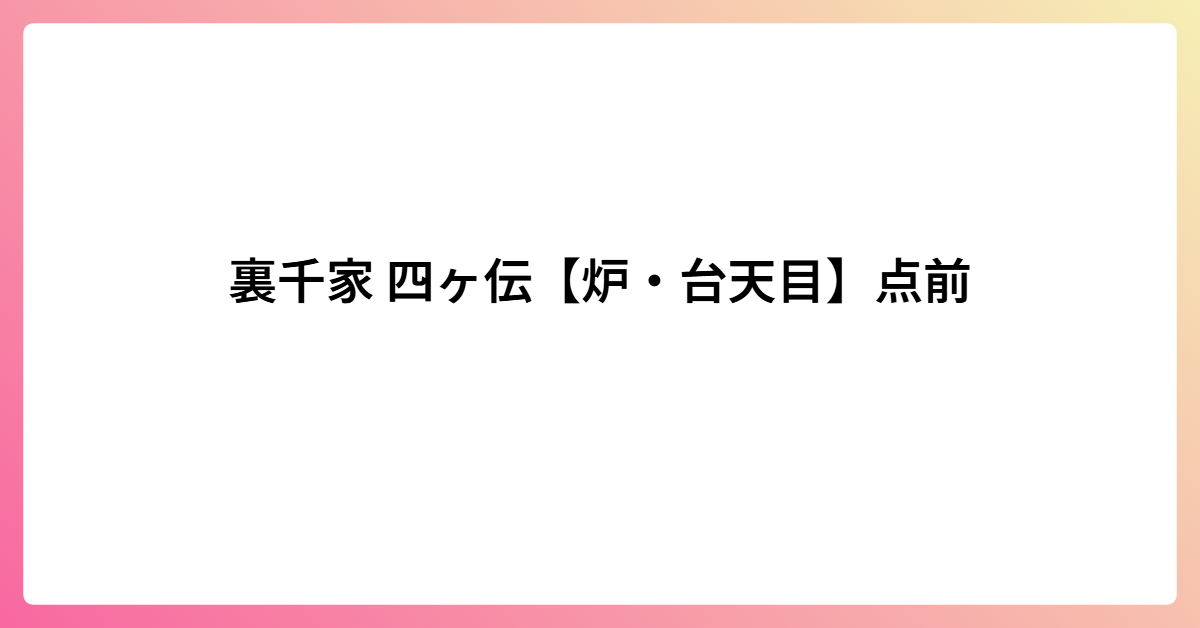
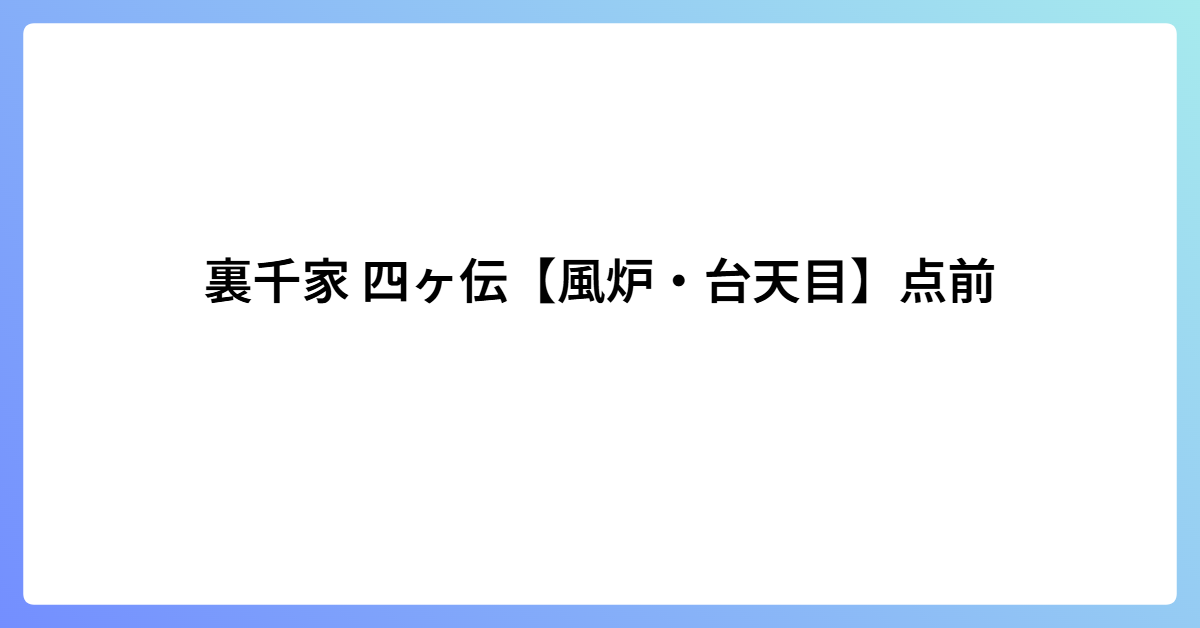
【風炉・唐物】はじめに準備しておくもの
- はじめから室内に置いておくもの
- お点前が始まるときに持って入るもの
- 膝退(しったい)して再入室するときに持って入るもの
| 構成 | 道具 |
|---|---|
| はじめから室内(影荘り) | 曲水指・唐物茶入 |
| 入室→膝退して退室 | 楽茶碗・茶巾・茶筅・節止めの茶杓 |
| 建水を持って再入室 | 唐金建水・竹蓋置・柄杓 |
【風炉・唐物】お点前の手順
影荘りから迎えつけの挨拶
・曲水指・唐物茶入の配置
・水指と唐物茶入の距離は1.5cmくらい
・お菓子を運ぶ
・迎えつけの挨拶
・手をついて襖を閉める(襖は下から30cmの位置を持つ)
茶碗を持って入室
・両手をつき、襖を開ける

風炉でも濃茶の場合は襖を閉めるから注意やで。
・茶碗を勝手付きに仮置き
・唐物茶入を膝前、真ん中に置き(両手で取る)、仕覆を左右と脱がせて茶入を膝前に置いたら仕覆を水の方(水指側)に打ち返して、右手で水指の左横、奥に置く
・帛紗を四方捌き(真)して、唐物茶入を清めたら(二引きして時計回りに胴拭き)帛紗を座布団にして、水指の正面に両手で置く
・下から三枚目、親指を下で取って、たたみ直して腰につける
・左手で茶碗を取り、右手で膝前に置き膝退
・建水を持って入ったら、襖を閉める

再度入室したら、膝行できるように居前の少し後ろ気味に座るようにしてな。
・膝行して柄杓を構え、蓋置を置いて柄杓を引いたら総礼
・建水を上げて居住いを正したら、帛紗を(草)で捌き、茶杓を三往復で清めたら唐物に斜めに立てかける
・茶筅は建水の右肩に置く
・茶巾は水指の蓋の上(唐物茶入を避けるようにして置く)
・柄杓を構えたら帛紗で釜の蓋を開けて、帛紗は建水の下
・茶碗に湯を注ぎ、茶筅通し(二度上げ三度打ち・さらさら・の)
・湯を捨て、茶巾で清めて茶碗を置き、茶巾を水指の上へ置く
濃茶を練る
・茶杓を茶碗の上(右側)に預ける
・両手で唐物を取り、蓋を取ったら(瓶子蓋の場合はひっくり返して置く)改めて茶杓を握る
・茶をすくい出し(回し出しはしない)※手の油をつけないよう、茶入の土を触らずに左手を丸めて釉薬部分を持つ
・茶杓を再び茶碗の上に預け、唐物茶入を両手で水指の前に戻したら茶をさばく
・茶杓を唐物茶入に斜めに立てかける
・水指の蓋を開けて、水一杓を釜に差して(湯相を整える)から茶を練る

風炉の時期のお茶は摘んでから時が経ってるから、いきなり熱い湯を注ぐと香味が飛んでまう。だから水を入れてちょうどいい湯加減にしてやるんやで。これも心遣いやな。
・茶を練ったあとも茶筅は建水の右肩
・茶碗を時計回りに二回まわして出す
茶に関する問答
・正客がひと口飲んだらお服加減を聞く

【亭主】いかがでございますか?

【正客】大変、結構でございます。
・亭主はお服加減を聞いたら客付に回って茶銘の問答

大変、結構なお茶をありがとうございました。お茶銘は?

吉祥の昔でございます。(松花の昔・松の嶺などもあるで)

お詰めは?(お詰めとは製造元のことね)

吉川園でございます。(小山園・三丘園などもあるで)

前席では数々のお菓子をありがとうございました。(四ヶ伝のお菓子は三種類・主菓子×2・水菓子【フルーツのこと】)
・居前に戻り、末客の吸いきりで中水(水を一杓)を差して帛紗を腰につける
・茶碗が返ってくる
・茶碗を膝前に取り込む
・総礼
仕舞い
・茶碗に湯を注ぎ、建水に捨てたら仕舞いの挨拶

お仕舞いにいたします。
・茶碗に水を注ぎ、茶筅通し(二度上げ三度打ち・さらさら・の)をしたら、茶巾は茶碗の中に入れる
・茶碗を置き、茶碗の中に茶筅を入れて右手で茶杓を持ち、建水を引く
・茶杓を清め(三往復)茶碗に伏せて置き、建水の上で帛紗を払って腰につける
・茶碗を二手(右横・左前)で勝手付きに仮置き
・水一杓(仕舞い水)を入れ、水指の蓋を閉める
・水指の蓋が閉まれば、拝見の声がかかる【割乞い】

どうぞ、お茶入の拝見を…

唐物は格が高いから、他の道具とは別々に拝見をお願いするんや。それを【割乞い】って言うんやで。
拝見に出す
・柄杓と蓋置を建水に伏せる
・唐物茶入を両手で持って客付に回る
・帛紗を四方捌き(真の行)に捌いて唐物茶入を清める
・唐物茶入を出す時は、帛紗を座布団にしてから反時計に二回まわして鐶付に出す
・帛紗の一枚目を親指上で取り、たたんで腰につける
・ここで正客が残りの道具の拝見を乞う

どうぞ、お茶杓、お仕覆の拝見を…
・茶杓を居前(正面)右手でとって左手に持ち替え、客付から左手をつきながら右手で出す(茶杓はいつもの位置)
・仕覆を居前(正面)右手でとり左手に受けて客付にまわり、左手をつきながら右手で出す(茶杓に仕覆の紐をかける)
道具を下げる
・建水一式
・茶碗一式
・水指(水指を下げるときに、手をついて襖を閉める)
・頃合いをみて再び入室
茶道具に関する問答
・道具の問答をする

ありがとうございました。お茶入は?

文琳でございます。

お茶杓は?

玄々斎精中でございます。

御銘は?

一期一会でございます。

お仕覆は?

永観堂金襴でございます。(色んな裂地があるで)

ありがとうございました。
道具を下げて退室
・右手で仕覆をとり、左手に受けたら、右手で茶杓をとり左手の仕覆の上に置く
・右手で唐物茶入をとる(左手も唐物茶入を迎えにいき、落下防止のため、唐物を左手で受けるようにしながら持ち退く)
・退室する(襖の開閉はすべて手をつく)
問答の道具例
・【唐物茶入】文琳・茄子
・【茶杓】玄々斎精中など
【風炉・唐物】客
【飲み方】
・縁内で茶碗を次客との間に置く
・客の間で総礼
・感謝して時計回りに二回まわして飲む
・懐紙で三回拭いたら、反時計回りに二回まわして次客におくる(送り礼・受け礼)
【拝見】
・拝見で引くときは、仕覆を茶杓にかけながら引く
・縁内に取り込む前に縁外で自分の膝前に近い方から唐物茶入・茶杓・仕覆の順に並べる
・唐物茶入は常に縁外に置く(唐物茶入以外を縁内に取り込んだら茶杓と仕覆はバラしてよい)
・拝見したら、もう一度、名残惜しむように全体を眺めて次客におくる
まとめ
大事なポイントは、
- 唐物は両手扱いであること
- 清め方が通常と逆であること
- 帛紗の扱いが【真】と【行】で異なること
この三点を常に意識したらいいで。
丁寧に学びながら、自分のものにしていこうな。
ほな、また!