裏千家 四ヶ伝【風炉・台天目】点前
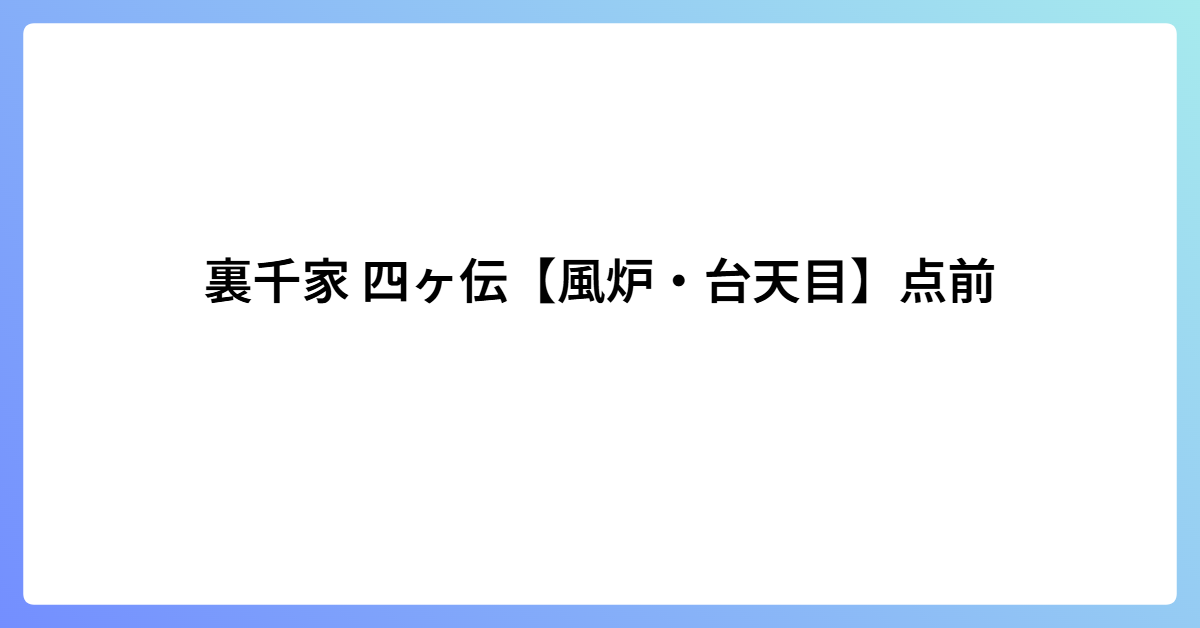
まいど、きょんたです!
この記事では、台天目のお点前の流れを整理しながら、【唐物】との違いや、よく間違えるポイントをわかりやすくまとめたで。
稽古の予習・復習に役立つ内容になってるから、ぜひ参考にしてな。
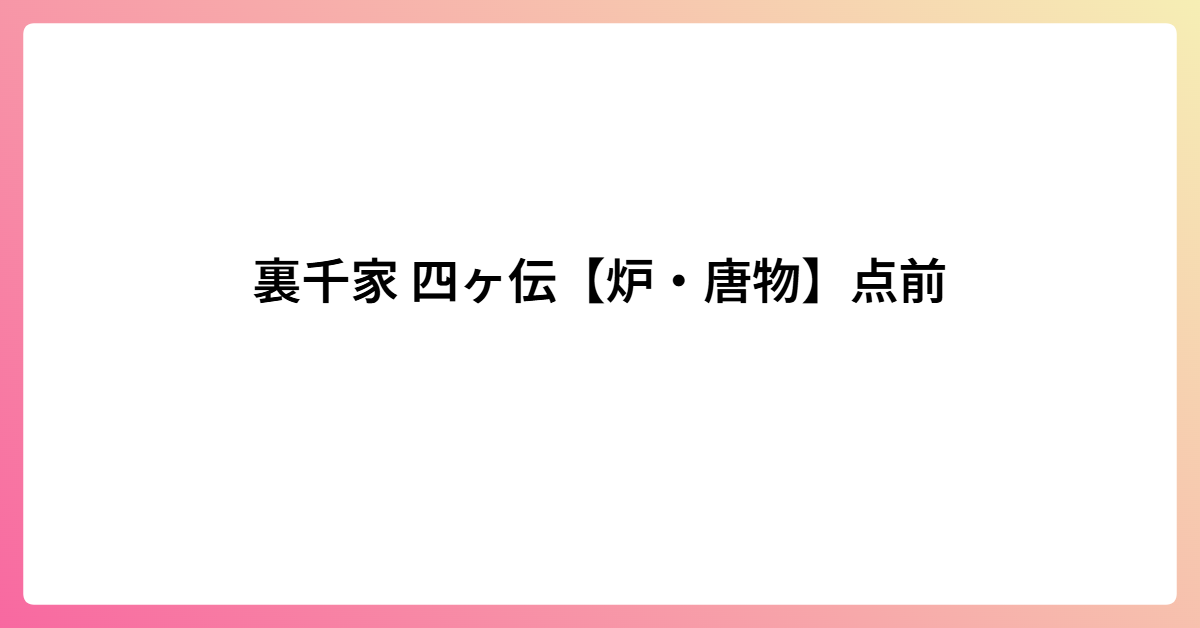
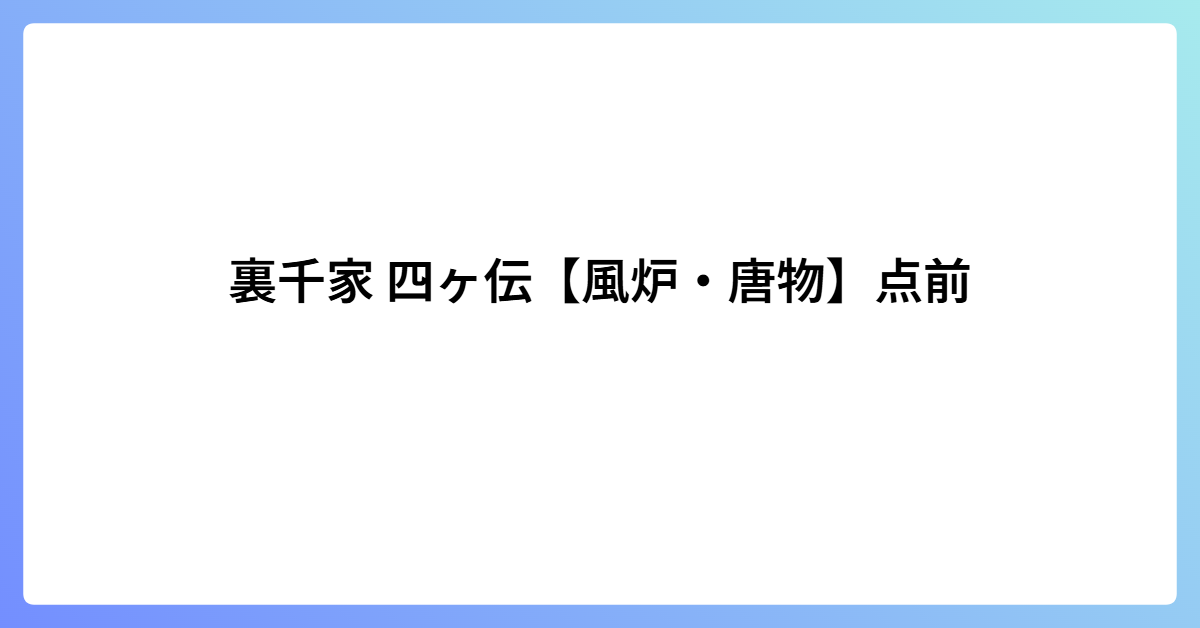
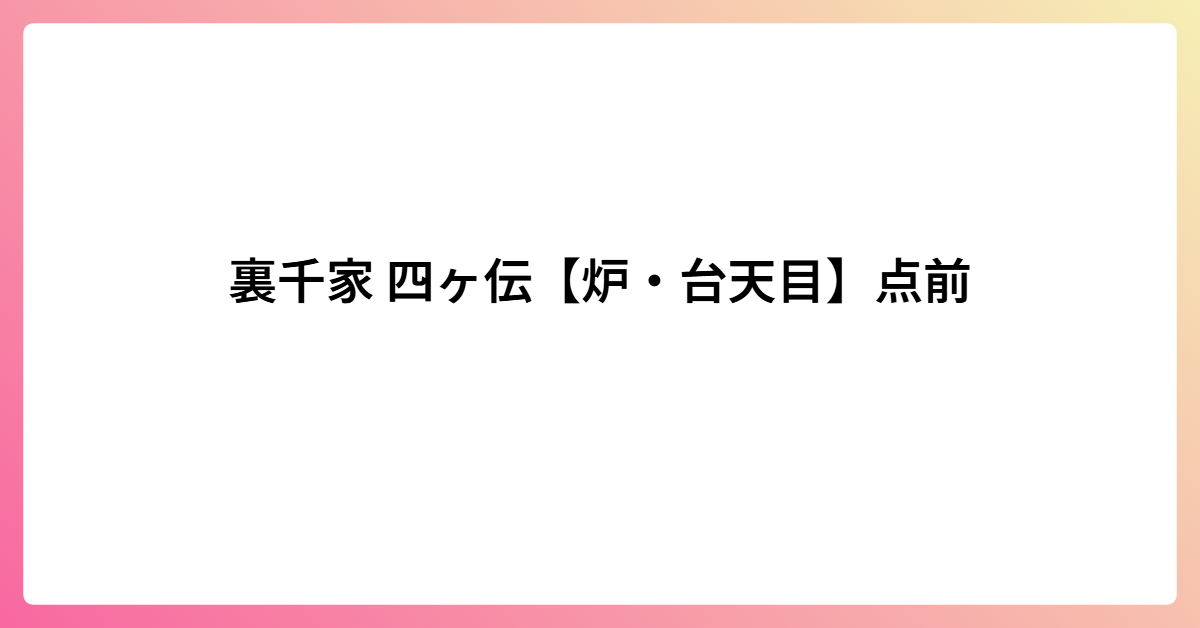
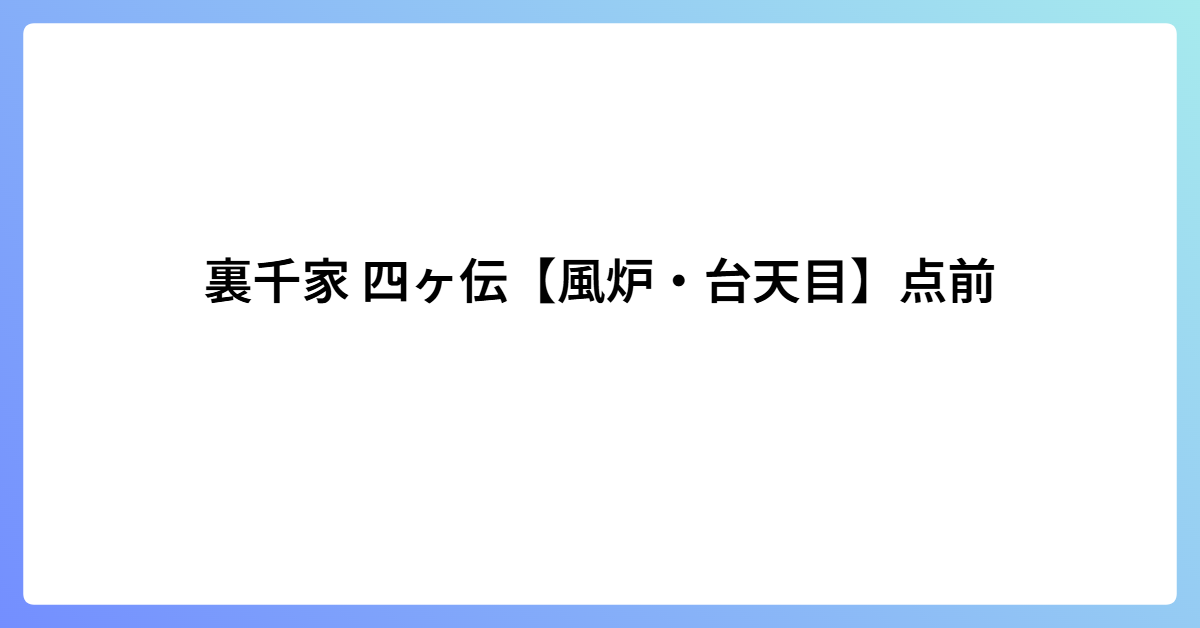
【風炉・台天目】事前準備
| 構成 | 道具 |
|---|---|
| はじめから室内(影荘り) | 曲水指・和物茶入・天目台・天目茶碗・象牙の茶杓・茶巾・茶筅 |
| 迎えつけの挨拶のあと | 唐金建水・竹蓋置・柄杓 |
お点前を始める前に、以下を茶室に事前準備
- 曲水指
- 和物茶入(水指前の右側に置く)
- 天目台・天目茶碗・象牙の茶杓・茶巾・茶筅(水指前の左側に置く)
迎えつけの挨拶後に建水を持って入室し、お点前開始
【風炉・台天目】お点前の手順
影荘りから迎えつけの挨拶
・曲水指を運び、その右前に和物茶入と左前に天目台一式を置く

台天目の三つ荘り(みつかざり)って覚えたらええで。
・天目茶碗と天目台は鬼灯(ほおずき)を割って持ち運ぶこと(天目台は左右で持つ)
・お菓子を運ぶ
・迎えつけの挨拶
・手をついて襖を閉める(襖は下から30cmの位置を持つ)
建水を持って入室
・両手をつき、襖を開ける

風炉でも濃茶の場合は襖を閉めるから注意やで。
・建水を手なりで置き、蓋置を置いて柄杓を構えてから引く(音は鳴らさない)

建水を持つときは体に沿わせて運んでな。
・総礼
・天目台を(左右)の順で持ち(左横・右前)、膝前奥に両手で置く(左横・右横)
・茶入を膝前、真ん中に置き(右手で取る)、仕覆を右左と脱がせて茶入を膝前に置いたら仕覆を火の方(釜側)に打ち返して、右手で水指の左横、奥に置く
・帛紗を四方捌き(草)して、茶入を清めたら(二引きして反時計回りに胴拭き)水指の左前に置く
・象牙の茶杓を清めて(三往復・一回突いて、二回抜いたあと、草に捌き直して清め拭き)茶入の蓋の上、左側(火の方・釜側)に置く

茶杓を拭くときはおもむろに拭くときれいなお点前になるで。櫂先が上を向かないように注意も必要やで。
・茶筅を出して水指の右前に置く
・茶巾を水指の蓋の上に置く
・柄杓を構えたら帛紗で釜の蓋を開けて、帛紗は建水の下
・左手を添えて茶碗に湯を注ぐ
・茶碗を右左で持ち、反時計回りに小濯ぎ三回(万が一の落下のため膝の上で回す)
・両手で湯を建水に捨て、右手で露切り

天目茶碗は覆輪があるから、湯や水を捨てると流れたところだけ色が変わってムラになる。だから露切りをして、全体が均等に変色するようにしてるんやで。
・茶碗を天目台に戻す(両手で包み込むように)
・再度、左手を添えて茶碗に湯を注ぎ、茶筅を入れ、両手で火窓前(天目座)に仮置き
・帛紗を真の真に捌いて天目台を清める(鬼灯手前を左から右、鬼灯向こうを左から右、羽の手前を左から右、向こうを左から右・天目台は浮かせる)
・帛紗を握り込んで両手で天目台を置く(お茶を点てやすい位置に)
・帛紗の上から三枚目、親指を上で取り、草に捌いて建水の下に置く
・火窓前から両手で茶碗を持ち、膝の上で茶筅通し(天目台に置かずに三度上げ三度打ち・さらさら・の)
・茶筅を右手で置いたあと、両手で湯を建水に捨て、茶巾で露切りしてそのまま茶碗を拭く

今まで両手で大事に持ってた茶碗やのに、茶筅を置く時は左手だけで持っとく。今までのは何やってん!ってなるな。笑
・茶巾で茶碗を拭いたら、天目台へ置く(茶巾は釜の蓋の上へ)
濃茶を練る
・茶杓を取り、茶碗に預ける

象牙の茶杓は重いから茶碗に預ける。って覚えたらいいで。
・茶入を左手で持ち、茶をすくい出し(回し出しはしない)
・茶をさばいて、象牙の場合は左手を添えながら茶碗の内側で優しく打つ
・茶杓を茶入の蓋の上に置いたら、水指の蓋を開けて、水一杓を釜に差して(湯相を整える)から濃茶を練る

風炉の時期のお茶は摘んでから時が経ってるから、いきなり熱い湯を注ぐと香味が飛んでまう。だから水を入れてちょうどいい湯加減にしてやるんやで。これも心遣いやな。
・左右の順で天目台の羽を持ち、客付に回る(天目台は低く持つ)
・下に置かずに、その場の低い姿勢で反時計回りに二回まわして鐶付に出す(左手を向こう、右手を手前にして反時計回りに二回まわす)
・鐶付に出したら、左右で膝退して控える
茶に関する問答
・正客がひと口飲んだらお服加減を聞く

【亭主】いかがでございますか?

【正客】大変、結構でございます。
・お服加減を聞いたら右左で膝行して茶銘の問答

大変、結構なお茶をありがとうございました。お茶銘は?

吉祥の昔でございます。(松花の昔・松の嶺などもあるで)

お詰めは?(お詰めとは製造元のことね)

吉川園でございます。(小山園・三丘園などもあるで)

前席では数々のお菓子をありがとうございました。(四ヶ伝のお菓子は三種類・主菓子・主菓子・水菓子【フルーツのこと】)
・末客の吸いきりで、中水(水を一杓)を差して帛紗を腰につける
・茶碗(天目台)が返ってくる
・茶碗(天目台)を膝前に取り込む
・総礼
・お茶碗と天目台の問答

お茶碗は?

油滴天目でございます。(灰被天目などもあるで)

お台は?

お茶碗に添ったものでございます。

ありがとうございました。
仕舞い
・茶碗に湯を注ぎ、小濯ぎを三回して両手で湯を建水に捨て、右手で露切り後、茶碗を天目台に置いたら仕舞いの挨拶

お仕舞いにいたします。
・茶碗に水を注ぎ、茶筅通しを(さらさら・打たずに三度上げ三度打ち・の)してから茶巾で露切りして茶碗を拭いたら、茶巾は茶碗の中に入れる
・茶碗を天目台に置き、茶碗の中に茶筅を入れて右手で茶杓を持ち、建水を引く
・茶杓を清め(三往復・一回突いて、二回抜く)建水の上で帛紗を払って、捌き直さずに清め拭き
・茶杓を茶碗に伏せて置き、帛紗を腰につける
・水指の前に天目台一式(左)と茶入(右)を置き合わせる
・水一杓(仕舞い水)を入れ、釜の蓋を閉めて柄杓を引いたら、水指の蓋を閉める
・水指の蓋が閉まれば、拝見の声がかかる

どうぞ、お茶入、お茶杓、お仕覆の拝見を…
拝見に出す
・柄杓と蓋置を建水に伏せる
・茶入を膝前に置き、天目台一式を水指の正面に置き直す
・茶入を左手に乗せて客付に回る
・四方捌き(草)をして、蓋を二引きし、胴拭きしたあと、帛紗を下に置いて二回時計回りにまわして出す(茶入は回し出しをしていないので口は清めない・蓋も外さない)
・帛紗を腰につける
・正面に戻って、茶杓を右手で取って左手に持ち替え、客付から手をついて右手で出す
・正面に戻って仕覆を右手で取り、左手に乗せ、客付から手をついて右手で出す
道具を下げる
・建水一式
・天目台一式
・水指(水指を下げるときに、手をついて襖を閉める)
・頃合いをみて再び入室
茶道具に関する問答
・道具の問答をする

ありがとうございました。お茶入は?

瀬戸の肩衝でございます。

お茶杓のお成りは?(象牙の茶杓は銘がないので、形状を聞くといいね。利休型・珠徳型があるよ)

利休型でございます。(珠徳型はちょっとぷっくりしてるで)

お仕覆は?

花丸金襴でございます。(色んな裂地があるで)

ありがとうございました。
道具を下げて退室
・右手で仕覆をとり、左手に受けたら、右手で茶杓をとり左手の仕覆の上に置く
・右手で茶入をとる
・退室する(襖の開閉はすべて手をつく)
問答の道具例
・【天目茶碗】油滴天目(ゆてき)・灰被天目(はいかつぎ)・梅花天目(ばいか)
・【天目台】盛阿弥・宗哲(塗師)
・【茶入】唐津肩衝・備前肩衝
【風炉・台天目】客
【飲み方】
・天目台は縁外で次客との間に置く
・客の間で総礼
・縁外で天目台ごと感謝
・膝前に古帛紗を広げて茶碗を置き、時計回りに茶碗を二回まわす
・両手で古帛紗ごと抱えるようにして飲む
・懐紙で三回拭いたら、反時計回りに二回まわして天目台に置く
・縁外で天目台ごと次客におくる(送り礼・受け礼)
【拝見】
・縁外で天目台全体を眺めたら、天目台の横に古帛紗を広げ、茶碗を拝見してから古帛紗の上に仮置く
・天目台を拝見したら茶碗を天目台に置き、古帛紗を懐中する
・もう一度、名残惜しむように全体を眺める
まとめ
【台天目】のお点前は天目茶碗が主役になるお点前。
これを押さえとけば、難しいと言われる【台天目】も、自信を持って取り組めるようになるで。
茶道のお点前は一朝一夕ではできへんから、繰り返し稽古してしっかり体に落とし込んでいこうな。
ほな、また!